詳細
自治ひょうご 連載記事「尾西が斬る!Vol.2」まとめ
阪神・淡路大震災から30年を節目に「災害に強い自治体」の実現や、労働組合が果たすべき役割、「人員確保の重要性」について再考したシリーズ「尾西が斬る!Vol.2」
自治ひょうごで2025年3月から7連載したものをまとめて再掲します。

大規模災害に対応できる人員配置

今回のシリーズでは、阪神淡路大震災から30年を期に、あらためて災害時における自治体の役割、そして私たち労働組合としての取り組みを考えていきます。
私たち自治体で働く職員は、いざ災害が起これば即座に対応しなければなりません。しかし、現状の人員不足の中で、30年前と同規模の災害が発生すれば、各自治体は対応できるのでしょうか。
30年前は、現業職場の存在も大きく、災害ゴミの撤収や仮設トイレのし尿収集、水の確保や避難所運営などに対応してきました。また、震災を経験した神戸市では、これまで多くの災害、震災に見舞われた自治体に対し、多くの支援を行ってきています。昨年発生した能登の大震災においても、震災ゴミの収集等の支援に多くの現業組合員が派遣されました。
私も東日本大震災の際に、宮城県に支援に入りましたが、阪神淡路大震災では、全国から自治労の仲間に1ヶ月で250人以上の支援をいただきました。
しかし今、兵庫県内の各自治体では、業務委託や退職者不補充、会計年度任用職員の活用などで、現業職員が年々減少しているのが現状です。さらに、事務職場もRPAやAIの導入により、より人員が削減される傾向にあります。このような状況では、大規模災害はおろか、各地で頻発する豪雨災害などにも対応できないことが明白です。
阪神淡路大震災から30年、兵庫県のキャッチフレーズは『うすれない記憶はない。つなぐべき決意がある』です。
大震災を経験した被災地で働く私たちは、人員不足が常態化した現状に異を唱え、改めて災害に対応できる自治体となるよう、人員確保を要求する役割を果たしていかなければなりません。市民の安心・安全を守るため、自治体当局に対し現場実態を突き付け、人員体制の整備を要求できるのは、自治体単組以外にありません。単組は春闘期から職場点検に入り、要求を確立してください。
次回以降、6月の人員確保闘争の要求等ついて触れていきます。
災害に強い自治体をめざして
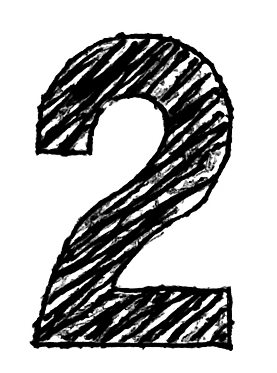
阪神・淡路大震災から30年となる節目の年。今年の人員確保闘争は災害対応を考えて取り組みを進めていきたいと思います。
振り返るとあっと言う間の30年。当時と比べて何が変わったのでしょうか。
国では、阪神・淡路大震災後、災害対策の法制度が整備され、地震観測・情報提供の体制などが大きく変わり、庁舎や公共施設なども耐震工事が進みました。
しかし、その反面、災害支援に携わった現業職場の多くは正規職員不補充や委託化の波に呑まれていきました。行政職場はより効率化を進め、機構改革やシステムの導入など、人員削減が進みました。
各自治体で、震災後にハード面の改善を図ってきていますが、人員配置を含めたソフト面は改善どころか後退しているのが現状ではないでしょうか。
たとえば直営でのゴミ収集は、ステーション管理を行う上で市内のことはすべて熟知しています。いざ災害が起これば危険箇所の判断を行い、すぐに業務を進めることができますが、民間業者では無理です。
しかし、それは民間業者が悪いわけではありません。直営と民間の大きな違いは、直営の職員は直ちに市民、住民のために動くことができるのに対し、民間は契約内容に基づいてしか動くことができないためです。現状でも危険箇所に関しては、直営でしかできない業務もあります。
これまで兵庫県本部は「直営堅持」を基本に取り組みを進めてきていますが、今一度、災害にもしっかりと対応できる直営の必要性を追及し、災害に強い自治体をめざさなければなりません。
現業職場は市民生活も含む環境を、学校給食・学校用務は教育の一環を、看護やコメディカル、病院給食は医療の一環を守っています。6月の人員確保闘争に向け、自治体としての災害対応のあり方や現業職の位置づけを明らかにさせ、正規職員補充や委託の再公営化などをめざして取り組みを進める必要があります。
次回は文化を守り、育てる行政職について考えていきます。
地域の歴史・文化を守り、未来へつなぐ
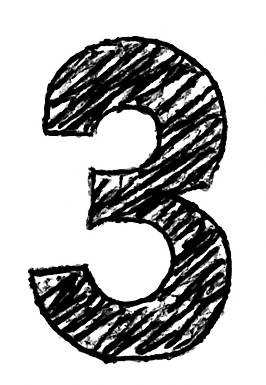
自治体の行政サービスの基本は、市民サービス、教育サービス、保健・医療・福祉サービス、公共工事サービス、環境管理サービス、防災サービスなどを進めることです。
それら業務には、そこに住む人々の暮らしやそれぞれの地域の文化や歴史を守ることが通底しています。
であるからこそ、自治体職員が、地域の文化や歴史、人々の暮らしを理解し業務を進めることで、さらに行政サービスが向上するのではないでしょうか。
今、各自治体で早期離職者の増加が大きな問題となっています。その対策として、賃金や職場環境の改善は必要不可欠ですが、さらに、その自治体で働くことにやりがい(ワークエンゲージメント)を持てるよう、地域の特色ある歴史や文化を知り、人々と繋がる機会や研修が必要となってきていると考えます。
震災以降、各自治体の業務は、財政難を理由に出先機関や窓口業務を中心に、指定管理者制度などを活用し委託化が進められてきました。そのなかで、地域の文化拠点である図書館も委託の波にのみ込まれていきました。
図書館の委託を推し進めてきたある自治体では、図書館を市民の憩いの場として、本の販売や飲食の提供などを行い、営利を追及し、貸館業務以上のサービスを追及しました。それらはサービス向上であると注目される影で、地域に精通した司書や貴重な地元の歴史書などが失われている側面があることも知らねばなりません。
それぞれの地域が、どことも違う独自の文化や歴史を持つことが、その地域たる所以であり、そこに住む人々が愛着を持つ理由であると言えます。自治体は、その独自性を守り継いでいく役割を重視しなければなりません。
阪神・淡路大震災から30年となる今年。30年、50年、100年先を見据え、本来の自治体業務は営利を追求する業務ではないことを改めて認識し、震災・災害にも対応でき、人々の暮らしや地域の歴史・文化を守ることのできる体制を構築していく必要があります。
災害に備える人員の確保に向けて

阪神淡路大震災から30年の節目に、改めて「災害に対応できる自治体のあり方」を考えるのが、このシリーズの主題です。
みなさんは「災害に対応できる」「災害に強い」と聞いて、具体的にどのような例を思い浮かべるでしょうか。
さまざまな建物の耐震化などインフラが整備されていることや、避難所や避難経路などの確保、住民の意識や備えなど、ハード・ソフトの両面からいろいろ考えられると思います。
今、国において第217回通常国会に「災害対策基本法等の一部を改正する法律案」が提出されています。趣旨としては「能登半島地震の教訓等を踏まえ、災害対策の強化を図るため」とし、①国による災害対応の強化、②被災者支援の充実、③インフラ復旧・復興の迅速化を柱とした内容となっています。
具体的には、地方自治体に保存食や簡易トイレといった災害用物資の備蓄状況を年1回、公表することを義務付けたり、ボランティア団体を事前登録する制度を創設し、自治体との連携を促進するとともに、活動に必要な実費を支給するとしています。
また、避難所だけでなく、自宅や車で避難生活を送る高齢者などへの福祉支援を充実させるほか、能登半島地震の状況を踏まえ、災害時に水道復旧のため事業者が私有地に立ち入れるようにすることも盛り込んでいます。
これら法案の内容からは、災害対応において自治体が果すべき役割が非常に多くあることがわかります。その災害対応の中心となる自治体組合員の知見や意見が反映されることが、制度充実のために重要となってきます。
各自治体では、通常業務をこなすのに支障がでるような人員不足の実態があります。法律が整備され、素晴らしい制度が確立されても、それを現場で進めていく職員が不足していれば、絵に描いた餅になります。
4月に新年度の人員体制が明らかになっています。6月の人員確保闘争に向け、災害時を想定した人員要求を進めてください。
あらためて災害を考える
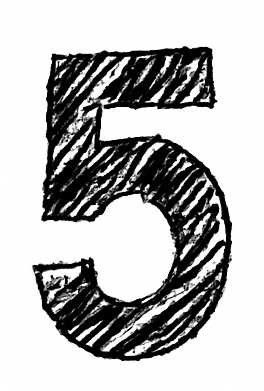
災害には、地震や台風、大雪などの自然災害だけでなく、人間の不注意や怠慢が原因で起こる「人災」もあります。
人為的な原因で社会に被害を与えるという意味で言えば、この間政府が行ってきたさまざまな施策も「災害」と呼べる側面があるのではないでしょうか。
「失われた30年」と言われるように、経済の停滞が続き、賃金が上がらない30年。自治体行政含め社会全体が非正規化へと舵を切り、低賃金化に拍車をかけました。
労働者供給事業は法律で原則禁止されてきましたが、1985年の労働者派遣法以降、規制が緩和され続け、人材派遣関連業は大きく成長しました。また、大手企業優遇の税制改革は、労働者の賃金を抑えたまま、企業の内部留保を増やすこととなりました。
労働者は低賃金のまま、より効率を上げることを求められ、「ブラック企業」「過労死」や「サービス残業」「メンタルヘルス」などの言葉が広がりました。それに対する労働者を守る働き方改革の取り組みが始まりましたが、使用者や当局の姿勢はまだまだ十分ではありません。
政府は戦争も大きな災害と位置づけ、国民を守ることを口実に、防衛強化として防衛費の引き上げを行ってきていますが、そもそも戦争を起こさない対策を進めることが必要だと思います。いつ発生するかもわからない自然災害に対し、防衛費よりも先に予算の確保を行い、各自治体に向け人員体制を含む準備を進める必要があります。
また、政府の施策により、自治体ではすでに「災害」が発生している状況です。
この30年、業務の効率化と称し、システムのイノベーション化など人員の抑制を進めてきました。結果、必要な人材は非正規職員で穴埋めを行い、不安定雇用と職場内の格差を生み、人員不足からメンタル疾患など人災が発生しています。
阪神淡路大震災から30年の節目となる今年、職場の諸課題も「災害」と位置づけ、災害に対応できる人員確保闘争に取り組みを進めていく必要があります。
市民を守るための人員確保
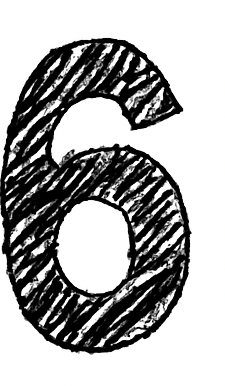
自治体の財政再建への対応策として、事業見直しのほか、職員賃金のカットによる人件費削減があります。公務員の賃金水準が高いという世論もあり、自治体としての財政縮減のアピールにもなることから、その選択がされることもしばしばあります。
しかし、人件費は義務的経費であり、職員の生活に直結するものなので、安易に削減できるものではありません。削減されたとしても、どこかで返金してもらわなければなりません。
採用難や早期退職で人材確保が困難な情勢のもと、自治体当局は人件費を抑制する方向ではなく、人材確保のための財政出動に舵を切る必要があります。
しかし、災害対応も含めた人材確保のための財政の確立は、一自治体の力だけでは難しいのが現実です。各自治体の首長は人気取りの耳障りのいい政策アピールだけでなく、大規模災害に対応できる体制整備や人材育成の必要性を強く認識し、責任を持って政府に訴え、財源を確保していく必要があります。
厳しい財政状況を人員削減や賃金カットという安易な方法で乗り切ろうとすると、負のスパイラルでさらに人員不足に拍車がかかり、自治体が崩壊しかねません。その先には、民間主導、営利優先の市民サービスとなってしまうのではないでしょうか。「自助」が強調され、本来保障されるべき公共サービスに対する受益者の負担を増やし、お金の無い者はサービスを受けれない、災害が起こっても助けてもらえない自治体運営となってしまうことも考えられます。
地方自治の最先端でその必要性を理解し、問題点の追及を含め、現場でその改善や拡充を行っていけるのは労働組合をおいて他にありません。
労働組合の取り組みの根幹である、組合員の賃金や働き方、人員の確保など、労働条件の改善を行うことは、最良の市民サービスにつながるものです。
各単組は、しっかりと交渉を進め、住民、市民を守る取り組みとなるよう人員確保闘争を進めていきましょう。
自信と誇りをもって取り組もう

今回のシリーズは、阪神淡路大震災から30年の区切りに、当時を振り返りながら、これからの人員確保闘争のあり方について考えてきました。最終回を迎えるにあたり、そのポイントを整理しておきます。
【災害対応を想定した人員の確保】
災害は人の命だけでなく、人が生活するための社会基盤に大きな打撃を与えます。しかし、現代の科学技術でも、地震や豪雨などの発生時期・場所・規模などを予測することは、困難な状況です。市民・住民の生活を守るためには、いつ災害が起きても対応できる人員体制を要求していく必要があります。
【正規化・再直営化】
この間、自治体財政を理由として、非正規化や委託化が進められてきました。いざ災害が起これば、これら委託・非正規の立場では災害業務に携わることが出来ないことを認識する必要があります。
会計年度任用職員の処遇改善を進め、正規化を目指す取り組みや、安易な委託化の阻止や再直営化の取り組みが、災害に強い自治体づくりにつながります。
【やりがいを持って働き続けるために】
自らが働く自治体について、歴史や文化、景観などを知り、市民・住民とのつながりをつくることは、職員が地域に愛着を感じ、やりがいを持って働くことに寄与します。そのための継続した研修や地域交流の場の設定、そして、それが可能な人員体制なども考えていかなければなりません。
また、職場の人間関係も重要な要素です。労働組合を基盤とした組合員同士の支え合い、助け合いのつながりを強めていく必要があります。
中途退職者の増加が課題となる中、賃金改善と併せ、職員のやりがいに視点をあてた取り組みが必要です。
【労働組合の役割】
働きやすい職場づくりや、格差是正、平和・人権の取り組みは、市民の生活を支え、より良い社会づくりに向けた、労働組合の社会的な役割です。自治労組合員であることに自信と誇りをもって取り組みを進めていきましょう。
